「湿疹とはどんな病気なの?」
「湿疹になる原因はなに?」
上記のような疑問をお持ちの方もいるのではないでしょうか。
湿疹とは、皮膚に水ぶくれや赤くブツブツした症状を伴う皮膚の炎症の総称のことです。
本記事では、上記の疑問を知りたい方はもちろん、「湿疹の診療方法や投薬される薬が知りたい」という方に向けて、湿疹の原因や症状などを解説します。
湿疹ができて悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。
湿疹はどんな病気?

湿疹とは、下記のような症状を伴う皮膚の炎症の総称のことをいいます。
- 赤らみ
- ブツブツ
- 水ぶくれ
- かゆみ
年齢層が幅広く、乳幼児〜高齢者までにみられるため馴染みのある病気といえます。
また、湿疹の炎症の原因やかゆみ、痛みといった症状の程度は多岐にわたるため、正しい判断が難しいのが特徴的です。
湿疹はなぜできる?湿疹の原因とは

湿疹の原因は、環境要因と内部要因の2種類に分けられます。
環境要因とは金属や花粉、ハウスダスト、薬剤、細菌といった外部からの刺激によるもので、内部要因は健康状態と皮膚の状態、アトピーの素因と自身の体質のことを指します。
また、上記の2つが組み合わさることで、異なる症状が見られることもあるので注意しましょう。
湿疹はどんな症状?

湿疹の症状は急性期(急に発症してしまう時期)と慢性期で異なり、急性期では下記のような症状が混在するといわれています。
炎症初期では、かゆみを伴う小さな赤いブツブツができます。発症した赤いブツブツのかゆみを酷く掻きすぎてしまうと、水ぶくれになったり真菌や細菌に感染したりして痛みや発熱、膿(うみ)が生じてしまうため注意しましょう。
湿疹の症状が悪化すると、水ぶくれが破けてしまうことや皮膚がただれ、皮膚に穴が開く「潰瘍(かいよう)」ができる可能性があります。
炎症初期が終わるとかさぶたができますが、かゆみによって再び掻いてしまうとかさぶたが剝がれ、皮膚のただれや潰瘍が悪化しますので注意が必要です。
また、慢性期の症状に関しては、急性期の症状を少し残しつつ皮膚が厚くなり盛り上がった状態となります。赤黒い色素が残ってしまったり、逆に脱色して皮膚が白く変色したりするケースもあります。
湿疹に違いはあるの?湿疹の種類とは

湿疹にはさまざまな種類があるので、湿疹の種類を下記の分類ごとに紹介します。
- 病因による分類
- 身体の部位による分類
- 症状による分類
それぞれの湿疹の特徴をまとめていますので参考にしてください。
湿疹の種類(1)病因による分類
病気の原因である「病因」で分類された湿疹を下記の表で紹介します。
| 接触皮膚炎 | ・アレルギー反応による湿疹 ・金属や食物、化粧品などが原因 |
|---|---|
| 脂漏性皮膚炎 | ・皮膚の常在菌が増殖することが原因ので引き起こされる湿疹 ・頭皮や鼻、わきの下など皮脂が過剰分泌されるところに多い |
| アトピー性皮膚炎 | ・アレルギー性の鼻炎アトピー素因を有している人に引き起こされる湿疹 |
| うっ滞性皮膚炎 | ・慢性湿疹 ・下肢の静脈の血流が滞ることが原因 |
病因による湿疹はアレルギーが原因で引き起こすことが多いといえます。
また、うっ滞性皮膚炎に関しては、長時間立っていると引き起こすことがあるため、立ち仕事をしている方は注意しましょう。
脂漏性皮膚炎について詳しく知りたい方は、下記記事を参考にしてください。
関連記事:脂漏性皮膚炎の原因とは?症状や治療方法、予防方法を解説
湿疹の種類(2)身体の部位による分類
身体の部位ごとに湿疹が発生する場合が有りますので、下記の表にて紹介します。
| 手湿疹 | 洗剤を使用した水仕事を頻繁に行っている場合にできる手荒れ |
|---|---|
| 舌なめずり皮膚炎 | 口や唇が乾燥した時にしたでなめることによって引き起こされる湿疹 |
| おむつ皮膚炎 | 乳幼児のおむつ装着部位に引き起こされる湿疹 |
部位ごとにケアをしなければ、上記のような湿疹ができてしまうため注意しましょう。特にお子さんをお持ちの方は、自分の手と赤ちゃんの湿疹のケアをするように心がけてください。
湿疹の種類(3)症状による分類
症状によって分類された湿疹を下記の表にて紹介します。
| 貨幣上湿疹 | ・貨幣上の赤い膨らみが生じる湿疹 ・乾燥によって引き起こされた湿疹を何度も搔きむしることが原因 |
|---|---|
| ビダール苔癬 | ・首の後ろやわきの下などに起こる慢性の湿疹 ・衣類による摩擦や金属アレルギーが原因 ・中年女性に多い |
上記の通り、何度も掻きむしってしまうことで引き起こされる湿疹もあるため、乾燥によるかゆみを起こさないためにも保湿を行うようにしましょう。
湿疹は薬で治る?湿疹の治し方とは

湿疹の治し方は、基本的にステロイドと呼ばれる薬を使用します。
なぜなら、ステロイドには抗炎症作用があるためです。皮膚が赤くなっている場合は、「皮膚が炎症を起こしている」状態のため、抗炎症作用のある薬が症状改善に作用します。
ステロイドの中でも、湿疹の症状が軽度で局所的な場合は塗り薬であるステロイド外用薬で対応し、全身に湿疹が生じてしまい重症な場合はステロイド内服薬で対応します。
また、真菌や細菌に感染している場合は、抗真菌薬や抗菌薬が使用され、かゆみの症状に対しては抗ヒスタミン薬の内服が適しています。
湿疹はどう診る?湿疹の検査・診断方法とは

湿疹はまず、問診を行い下記の事柄について詳しく聞かれます。
- 発症部位
- 状況
- 原因
- 症状
上記の問診を終えると発症部位の色や形を診察し、アレルギーが原因の可能性が高い場合はアレルギー検査を行い、内科の病気が疑われた場合は血液検査を行います。
湿疹に関するよくある質問
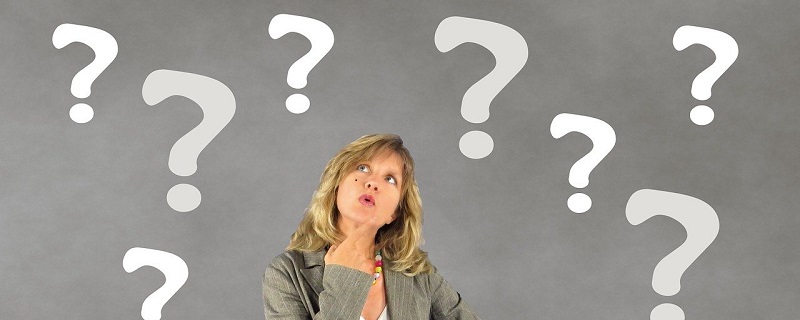
最後に、湿疹についてよくある質問について回答します。
かゆみを伴う湿疹が慢性的に繰り返されていた場合、アトピー性皮膚炎の可能性があります。
皮膚のバリア機能が低下し、個人の有している体質・免疫免疫学的要因とにさまざまな刺激が加わることで発症します。
また、アルミやニッケルなど外部からの刺激で湿疹が引き起こされた場合は、金属アレルギーと予想できるでしょう。
湿疹と発疹の違いは、病名か症状かの違いです。
具体的には、発疹や倦怠感は「症状」で、湿疹や蕁麻疹、インフルエンザは病名です。そのため、発疹は湿疹によって起こるものとなります。
Q湿疹の原因はストレスなんですか?
湿疹の一種である「脂漏性皮膚炎」は主にストレスが原因だと考えられています。
ストレス以外にも、下記のような事象も原因とされています。
- ビタミン不足
- ホルモンバランスの乱れ
- 不規則な生活
- ストレス
- 疲労
- 寝不足
上記の事象が原因で皮脂のバランスが乱れると湿疹が起きてしまう可能性があります。
脂漏性皮膚炎について詳しく知りたい方は下記の記事を参考にしてください。
関連記事:脂漏性皮膚炎の原因とは?症状や治療方法、予防方法を解説
東京で湿疹の治療ならアイシークリニックへご相談ください
湿疹は、悪化してしまうと潰瘍ができてしまう可能性があるため、注意しましょう。
治療後に傷跡が残る可能性を少しでも減らすためにも、もし体に湿疹のようなものができたら、その段階でご相談に来ていただくことをおすすめしています。
湿疹ができてしまった場合は、炎症度合いにかかわらず湿疹が悪化する前にアイシークリニックへご相談ください。
湿疹の予防方法とセルフケア
基本的な予防策
湿疹の発症や悪化を防ぐには、日常生活での予防とセルフケアが非常に重要です。予防策を実践することで、湿疹の再発リスクを大幅に減らすことができます。
スキンケアの基本原則
適切なスキンケアは湿疹予防の基盤となります。皮膚のバリア機能を維持するために、以下の点を心がけましょう。
まず、保湿が最も重要です。皮膚が乾燥すると外部刺激に対する抵抗力が弱まり、湿疹が発症しやすくなります。入浴後5分以内に保湿剤を塗布することで、水分の蒸発を防ぎ皮膚のバリア機能を維持できます。保湿剤は一日2〜3回、特に乾燥しやすい部位には頻繁に塗布することをおすすめします。
次に、適切な洗浄方法を実践することが大切です。熱すぎるお湯での入浴や、強くこすりすぎる洗い方は皮膚のバリア機能を損傷させます。38〜40度程度のぬるめのお湯で、石鹸やボディソープは肌に優しい低刺激性のものを選び、泡で優しく洗うようにしましょう。
環境調整による予防
住環境の調整も湿疹予防において重要な要素です。
室内環境の管理
適切な室内環境を維持することで、環境要因による湿疹発症を予防できます。室内の湿度は50〜60%を目安に保ちましょう。湿度が低すぎると皮膚の乾燥が進み、高すぎるとカビやダニの繁殖を促進します。
空気清浄機の使用や定期的な換気により、花粉やハウスダストなどのアレルゲンを除去することも効果的です。特にアレルギー性皮膚炎を持つ方は、寝具の定期的な洗濯や掃除機での清掃を心がけてください。
衣類の選択
直接肌に触れる衣類の素材選択も重要です。綿や麻などの天然素材は肌に優しく、通気性が良いため湿疹予防に適しています。化学繊維や毛製品は肌への刺激となる場合があるため、敏感肌の方は避けることをおすすめします。
また、衣類の洗濯時には無香料・無着色の洗剤を使用し、柔軟剤の使用は控えめにすることで、化学物質による皮膚刺激を最小限に抑えられます。
生活習慣と湿疹の関係
食事と栄養管理
食事は皮膚の健康に大きな影響を与えます。バランスの取れた栄養摂取により、皮膚のターンオーバーを正常化し、免疫機能を向上させることができます。
皮膚に良い栄養素
ビタミンAは皮膚の新陳代謝を促進し、バリア機能を強化します。人参、ほうれん草、レバーなどに豊富に含まれています。
ビタミンCは抗酸化作用があり、皮膚の修復を助けます。柑橘類、キウイフルーツ、ブロッコリーなどから摂取できます。
ビタミンEも抗酸化作用があり、皮膚の老化防止に役立ちます。ナッツ類、植物油、魚類に多く含まれています。
オメガ3脂肪酸は炎症を抑制する効果があります。青魚、亜麻仁油、くるみなどから摂取できます。
避けるべき食品
一方で、湿疹を悪化させる可能性のある食品もあります。過度に香辛料の効いた食べ物、アルコール、カフェインの過剰摂取は皮膚の炎症を悪化させる可能性があります。
また、個人のアレルギー反応を起こす食品(卵、牛乳、小麦、大豆、ナッツ類など)は避ける必要があります。食物アレルギーが疑われる場合は、専門医による検査を受けることをおすすめします。
睡眠と ストレス管理
十分な睡眠と適切なストレス管理は、皮膚の健康維持に欠かせません。
睡眠の重要性
睡眠中には成長ホルモンが分泌され、皮膚の修復や再生が活発に行われます。睡眠不足は免疫機能の低下を招き、湿疹の発症や悪化のリスクを高めます。理想的には7〜8時間の質の良い睡眠を確保しましょう。
寝室環境も重要です。室温は20〜22度、湿度は50〜60%に保ち、清潔な寝具を使用することで、睡眠の質を向上させられます。
ストレス対策
慢性的なストレスは免疫系に悪影響を与え、湿疹の悪化要因となります。効果的なストレス管理方法を見つけることが大切です。
深呼吸法や瞑想、ヨガなどのリラクゼーション技法は、交感神経の過度な活動を抑制し、皮膚の状態改善に役立ちます。
定期的な運動も有効です。適度な運動は血行を促進し、ストレスホルモンの分泌を抑制します。ただし、発汗による刺激で湿疹が悪化する場合があるため、運動後はすぐにシャワーを浴び、清潔な状態を保つことが重要です。
湿疹の重症度分類と対応
軽度湿疹の特徴と対処法
軽度の湿疹は、限局的な赤みや軽いかゆみを伴う状態です。この段階では、適切なセルフケアで症状の改善が期待できます。
患部を清潔に保ち、刺激を避けることが基本となります。かゆみがあっても掻かないよう注意し、冷たいタオルで患部を冷やすとかゆみが和らぎます。市販の低刺激性保湿剤を使用し、皮膚のバリア機能をサポートしましょう。
中等度湿疹の管理
中等度の湿疹は、明らかな炎症症状と持続的なかゆみを特徴とします。この段階では医療機関での治療が必要となります。
医師から処方されるステロイド外用薬を適切に使用し、症状の改善を図ります。使用方法や期間については医師の指示に従い、自己判断での中断や継続は避けましょう。
また、かゆみ対策として抗ヒスタミン薬の内服も併用される場合があります。日常生活では、患部への刺激を最小限に抑え、適切なスキンケアを継続することが重要です。
重症湿疹の治療アプローチ
重症湿疹では、広範囲にわたる炎症や強いかゆみ、二次感染の併発などが見られます。この場合は集中的な治療が必要となります。
全身への影響を考慮し、ステロイド内服薬や免疫抑制剤の使用が検討されます。重症例では入院治療が必要となる場合もあります。
患者様の年齢、症状の程度、合併症の有無などを総合的に評価し、個別化された治療計画を立案します。
年齢別の湿疹の特徴と対策
乳幼児の湿疹管理
乳幼児期は皮膚のバリア機能が未熟で、湿疹を発症しやすい時期です。特に生後2〜3ヶ月頃から湿疹が現れることが多く、適切な対応が必要です。
日常ケアのポイント
乳幼児のスキンケアでは、刺激の少ない石鹸やボディソープを使用し、ぬるめのお湯で短時間の入浴を心がけます。入浴後は速やかに保湿剤を塗布し、皮膚の乾燥を防ぎましょう。
爪を短く切り、掻きむしりによる皮膚損傷を防ぐことも重要です。夜間のかゆみ対策として、手袋やミトンの使用も効果的です。
離乳食開始時期には、新しい食材を一つずつ少量から導入し、アレルギー反応の有無を慎重に観察しましょう。食物アレルギーが湿疹悪化の原因となる場合があります。
学童期・思春期の湿疹対策
学童期から思春期にかけては、学校生活や部活動での発汗、制服による摩擦など、新たな刺激要因が増加します。
この時期の対策として、汗をかいた後の清拭や着替えを習慣化し、皮膚を清潔に保つことが大切です。また、ストレスが湿疹悪化の要因となることが多いため、学業や人間関係のストレス管理も重要になります。
思春期には皮脂分泌の増加により脂漏性皮膚炎が発症しやすくなります。適切な洗顔と保湿のバランスを保ち、過度な洗顔は避けるよう指導します。
成人期の湿疹管理
成人期の湿疹は、職業性接触皮膚炎や手湿疹が多く見られます。特に医療従事者、美容師、清掃業従事者など、化学物質や水に接触する機会の多い職種では注意が必要です。
作業時の保護具着用、作業後の適切な手洗いと保湿を徹底し、職業性皮膚炎の予防に努めましょう。また、化粧品による接触皮膚炎も成人女性に多く見られるため、新しい化粧品を使用する際は事前にパッチテストを行うことをおすすめします。
高齢者の湿疹ケア
高齢になると皮膚の水分保持能力が低下し、乾燥性湿疹が発症しやすくなります。また、皮膚のターンオーバーが遅くなり、傷の治りも遅くなるため、より丁寧なケアが必要です。
高齢者の場合、過度な清拭は皮膚の乾燥を助長するため、入浴頻度や洗浄方法を調整し、保湿を重点的に行います。また、薬物代謝の変化により薬効や副作用が若年者と異なる場合があるため、医師と密な連携を取りながら治療を進めることが重要です。
季節ごとの湿疹対策
春の対策
春は花粉の飛散時期であり、花粉による接触皮膚炎や既存の湿疹の悪化が起こりやすい季節です。
外出時はマスクや帽子、長袖の着用により皮膚への花粉付着を最小限に抑えます。帰宅後は速やかに衣類を着替え、洗顔・洗髪により花粉を除去しましょう。
また、気温の変化が激しい時期でもあるため、衣類による調温と適切な室内環境の維持が重要です。
夏の対策
夏季は高温多湿により発汗量が増加し、汗による刺激で湿疹が悪化しやすくなります。
こまめな汗の拭き取りと着替えを心がけ、吸湿性・通気性の良い衣類を選択しましょう。エアコンの使用により室内環境を調整し、過度な発汗を防ぎます。
日焼けも皮膚に強い刺激を与えるため、日焼け止めクリームの使用や帽子・長袖による紫外線対策を徹底します。ただし、日焼け止めクリーム自体が刺激となる場合があるため、敏感肌用の製品を選び、帰宅後は丁寧に洗い流しましょう。
秋の対策
秋は空気が乾燥し始め、皮膚の水分量が減少しやすい時期です。夏の間に受けた紫外線ダメージの影響も現れやすくなります。
保湿ケアを強化し、加湿器の使用を開始することで皮膚の乾燥を防ぎます。また、季節の変わり目はストレスや疲労が蓄積しやすいため、十分な休息と規則正しい生活リズムの維持を心がけましょう。
冬の対策
冬は一年で最も皮膚が乾燥しやすい季節であり、乾燥性湿疹の発症リスクが高まります。
暖房器具の使用により室内の湿度がさらに低下するため、加湿器を併用し適切な湿度を維持します。入浴時の温度や時間に特に注意し、入浴後の保湿ケアを丁寧に行いましょう。
静電気の発生により衣類による刺激が増加するため、静電気防止スプレーの使用や天然素材の衣類選択が効果的です。
湿疹と併発しやすい疾患
アレルギー性疾患との関連
湿疹患者の多くは、他のアレルギー性疾患も併発する傾向があります。これをアレルギーマーチと呼び、乳幼児期の食物アレルギーから始まり、アトピー性皮膚炎、気管支喘息、アレルギー性鼻炎へと進展することがあります。
早期からの適切な管理により、アレルギーマーチの進展を予防することができます。皮膚症状だけでなく、呼吸器症状や消化器症状にも注意を払い、総合的なアレルギー管理を行うことが重要です。
感染症のリスク
湿疹により皮膚のバリア機能が低下すると、細菌や真菌、ウイルスによる二次感染のリスクが高まります。
特に黄色ブドウ球菌による感染は湿疹患者に多く見られ、症状の急速な悪化や発熱を引き起こす可能性があります。患部に膿や臭い、発熱が認められる場合は、速やかに医療機関を受診し適切な抗菌治療を受けることが必要です。
ヘルペスウイルスによる感染(カポジ水痘様発疹症)も重篤な合併症の一つです。急激な悪化や水疱形成が見られる場合は、緊急受診が必要となります。
最新の湿疹治療法
外用免疫調節薬
従来のステロイド外用薬に加えて、カルシニューリン阻害薬(タクロリムス軟膏、ピメクロリムスクリーム)が使用されるようになりました。
これらの薬剤は非ステロイド性の抗炎症薬であり、特に顔面や頚部などのステロイド外用薬による副作用が懸念される部位での使用に適しています。長期使用によるステロイドの副作用を回避しながら、効果的な治療が可能です。
生物学的製剤
重症アトピー性皮膚炎に対する生物学的製剤(デュピルマブ、トラロキヌマブ、ネモリズマブなど)の使用が可能になりました。
これらの薬剤は特定の炎症性サイトカインや受容体を標的とし、従来の治療で十分な効果が得られなかった患者様にも良好な治療成績を示しています。投与は皮下注射により行われ、定期的な外来通院が必要となります。
JAK阻害薬
経口JAK阻害薬(バリシチニブ、ウパダシチニブ、アブロシチニブ)も新しい治療選択肢として登場しています。
炎症シグナル伝達を阻害することで、かゆみと炎症の両方に効果を発揮します。外用薬での治療が困難な患者様や、生物学的製剤が適用できない場合の選択肢となります。
湿疹治療における副作用と注意点
ステロイド外用薬の適切な使用
ステロイド外用薬は湿疹治療の基本となる薬剤ですが、適切な使用方法を理解することが重要です。
強度分類と部位別使用
ステロイド外用薬は強度により5段階に分類されます。顔面や陰部などの皮膚が薄い部位には弱いステロイドを、体幹や四肢には症状に応じて中等度以上のステロイドを使用します。
使用量の目安として、成人の人差し指の先端から第一関節までに出した量(FTU:Finger Tip Unit)で、成人の手のひら約2枚分の面積を塗布できます。
副作用の予防と対処
長期間の使用により皮膚萎縮、毛細血管拡張、紫斑などの副作用が現れる可能性があります。定期的な医師の診察により副作用の有無を確認し、必要に応じて薬剤の変更や休薬を行います。
ステロイド恐怖症により治療を避ける患者様もいますが、適切な使用であれば安全性は高く、症状改善による生活の質向上を期待できます。不安がある場合は医師に相談し、正しい知識を得ることが大切です。
免疫抑制薬の管理
重症例で使用される免疫抑制薬(シクロスポリン、メトトレキサートなど)では、感染症リスクの増加や肝機能・腎機能への影響が懸念されます。
定期的な血液検査により薬剤の血中濃度や臓器機能をモニタリングし、副作用の早期発見に努めます。感染症予防として、人込みを避ける、手洗い・うがいを徹底するなどの対策も必要です。
湿疹患者の心理的サポート
心理的影響への理解
慢性的な湿疹は単なる皮膚疾患にとどまらず、患者様の精神的健康に大きな影響を与えます。
かゆみによる睡眠障害は日中の集中力低下や疲労感を引き起こし、学業や仕事の能力に影響を与えます。また、見た目の変化により社会的活動への参加を控える患者様も多く、社会的孤立やうつ症状のリスクが高まります。
心理的サポートの重要性
患者様の不安や悩みに耳を傾け、共感的な態度で接することが治療効果の向上につながります。疾患に対する正しい知識の提供により、過度な不安や誤解を解消できます。
重度の心理的症状が認められる場合は、精神科や心療内科との連携も検討します。カウンセリングや認知行動療法により、疾患と上手に付き合う方法を学ぶことができます。
患者会やサポートグループ
同じ疾患を持つ患者様同士の情報交換や相互支援は、疾患管理において重要な役割を果たします。
患者会への参加により、実体験に基づくケア方法や治療情報を共有でき、精神的な支えを得ることができます。また、患者様ご自身が疾患について学び、主体的に治療に参加する意識の向上も期待できます。
湿疹治療の今後の展望
個別化医療の進歩
遺伝子検査や皮膚機能検査の発達により、個々の患者様に最適化された治療法の選択が可能になってきています。
バイオマーカーの測定により治療効果の予測や、副作用リスクの評価が行えるようになり、より安全で効果的な治療が提供できるようになることが期待されます。
新規治療薬の開発
現在、多くの新規治療薬の開発が進められています。経皮ワクチン療法、幹細胞治療、マイクロバイオーム治療など、従来とは異なるアプローチの治療法が研究されています。
これらの新しい治療法により、現在の標準治療では十分な効果が得られない患者様にも、より良い治療選択肢を提供できるようになる可能性があります。
日常生活での実践的アドバイス
入浴とスキンケアルーチン
効果的なスキンケアルーチンの確立は、湿疹管理の基本となります。
入浴方法
38〜40度のぬるめのお湯で10〜15分程度の入浴を目安とします。熱いお湯は皮膚の乾燥を促進するため避けましょう。石鹸やボディソープは弱酸性で無香料のものを選び、泡立てネットを使用して豊富な泡で優しく洗います。
洗髪時はシャンプーやリンスが身体に付着しないよう注意し、洗い残しがないよう丁寧にすすぎます。
保湿ケア
入浴後5分以内の保湿が理想的です。皮膚が湿っている状態で保湿剤を塗布することで、水分の蒸発を効果的に防げます。
保湿剤の選択では、ワセリンベースのクリームや軟膏が高い保湿効果を発揮します。ただし、べたつきが気になる場合は、日中はローションタイプ、夜間はクリームタイプと使い分けることも可能です。
衣類と寝具の管理
皮膚に直接触れる衣類と寝具の選択・管理は、湿疹の悪化予防において重要な要素です。
衣類選択のポイント
天然素材(綿、麻、シルクなど)を優先的に選び、化学繊維や毛製品は刺激となる可能性があるため避けることをおすすめします。衣類は少し余裕のあるサイズを選び、皮膚への摩擦を最小限に抑えましょう。
新しい衣類は使用前に一度洗濯し、製造時の化学物質を除去します。洗濯時は無香料・無着色の洗剤を使用し、柔軟剤の使用は控えめにします。
寝具の管理
枕カバーやシーツは週2〜3回の頻度で交換し、ダニやアレルゲンの蓄積を防ぎます。防ダニ加工の寝具カバーの使用も効果的です。
布団は定期的に天日干しし、掃除機での清掃も併用します。ダニの繁殖を抑制するため、寝室の湿度管理も重要です。
食事と栄養指導
湿疹の改善には、内側からのケアも重要です。バランスの取れた栄養摂取により皮膚の健康状態を向上させることができます。
推奨される栄養素
亜鉛は皮膚の修復と再生に重要な役割を果たします。牡蠣、牛肉、豆類などから摂取できます。
ビタミンD3は免疫機能の調節に関与し、適切な摂取により湿疹症状の改善が期待できます。魚類、卵黄、きのこ類に含まれています。
プロバイオティクス(乳酸菌、ビフィズス菌)は腸内環境を整え、免疫機能の正常化に寄与します。ヨーグルト、発酵食品の定期的な摂取をおすすめします。
制限すべき食品
個人差はありますが、湿疹を悪化させる可能性のある食品があります。アルコール、過度な香辛料、添加物の多い加工食品は炎症を促進する可能性があるため、摂取量に注意が必要です。
ただし、過度な食事制限は栄養不足を招き、かえって皮膚状態を悪化させる場合があります。医師や栄養士と相談しながら、バランスの取れた食事計画を立てることが重要です。
緊急時の対応
受診すべき症状
湿疹の症状が以下のような状態になった場合は、速やかに医療機関を受診してください。
急激な症状悪化、広範囲への拡散、高熱を伴う場合は細菌感染や重篤な皮膚炎の可能性があります。また、呼吸困難、全身の腫れ、意識レベルの低下などアナフィラキシーショックを疑う症状が現れた場合は、救急受診が必要です。
応急処置方法
医療機関受診までの応急処置として、患部を清潔に保ち、冷たいタオルで冷却することでかゆみや炎症を和らげることができます。
掻きむしりを防ぐため、爪を短く切り、必要に応じて手袋を着用します。市販の抗ヒスタミン薬の服用も、かゆみの軽減に効果があります。
ただし、自己判断での薬剤使用は症状悪化のリスクがあるため、可能な限り速やかに専門医の診察を受けることをおすすめします。
セカンドオピニオンと専門医連携
治療選択における判断
湿疹治療では、患者様の症状や生活状況に応じた個別化されたアプローチが必要です。現在の治療で十分な効果が得られない場合や、治療方針について疑問がある場合は、セカンドオピニオンを求めることも重要な選択肢の一つです。
特に重症例や難治性湿疹では、皮膚科専門医、アレルギー専門医、免疫学専門医など複数の専門医による連携治療が効果的です。
継続的な医療連携
湿疹は慢性疾患であることが多く、長期的な管理が必要です。定期的な診察により症状の変化を評価し、治療方針の調整を行います。
患者様自身も症状の変化や治療効果を記録し、医師との情報共有を積極的に行うことで、より良い治療成果を得ることができます。症状日記やかゆみスケールの活用により、客観的な評価が可能になります。
まとめ
湿疹は適切な知識と継続的なケアにより、症状の改善と生活の質の向上を図ることができる疾患です。個々の患者様の状態に応じた包括的なアプローチにより、最適な治療成果を目指しましょう。
何らかの皮膚症状でお悩みの場合は、早期の専門医相談をおすすめします。適切な診断と治療により、健康な皮膚状態の回復と維持が可能です。
監修者医師
高桑 康太 医師
略歴
- 2009年 東京大学医学部医学科卒業
- 2009年 東京逓信病院勤務
- 2012年 東京警察病院勤務
- 2012年 東京大学医学部附属病院勤務
- 2019年 当院治療責任者就任
佐藤 昌樹 医師
保有資格
日本整形外科学会整形外科専門医
略歴
- 2010年 筑波大学医学専門学群医学類卒業
- 2012年 東京大学医学部付属病院勤務
- 2012年 東京逓信病院勤務
- 2013年 独立行政法人労働者健康安全機構 横浜労災病院勤務
- 2015年 国立研究開発法人 国立国際医療研究センター病院勤務を経て当院勤務